福島拠点の協働の取り組み
令和6年度において、福島地域協働研究拠点(以下、福島拠点)は、地球科学や環境に関心をもつ福島県立安積黎明高等学校2年生のみなさんの探究をサポートしています。 「総合的な探究の時間」では、高校生が自分自身の興味や素朴な疑問をもとに問いを立て、その問いを明らかにするため探究を行っています。
この記事では、「総合的な探究の時間」で福島拠点の研究者による講義を受けた生徒たちが、その中で扱われたテーマをもとに探究を深め、中間発表を通じて研究的な手法にチャレンジした様子をお伝えします。
過去の活動報告はこちら:
講義と対話で環境を考える。私たちの持続可能な社会[安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告②]
高校生の探究をサポート。講義と対話で環境を考える[安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告①]
高校生の探究をサポート
福島拠点の研究者による4回の講義の後、11月に予定されている中間発表に向けて生徒たちは6つのグループに分かれ、夏休み明け以降三か月間をかけて探究を行いました。
各グループは独自の「問い」を設定し、探究を進めた成果をスライドにまとめました。
中間発表に向けて、福島拠点の研究者が、自身が行っている研究内容に絡めて、問いの立て方から検証の方法、考察のポイントや資料のまとめ方まで、対話やアドバイスを通じて支援を行いました。
中間発表では、各グループ5分を持ち時間とし、20人以上いるゼミのメンバーの前に立ち探究の成果を発表し、意見交換や質疑応答を行いました。 聞き手の目の前に立ち発表するため、反応が手に取るようにわかります。
福島拠点からいつも探究に参加しているメンバーだけでなく、講義を担当した五味室長と田中特別研究員 も参加し、研究者の視点から講評を行いました。
研究者の前で発表することに生徒たちは緊張を隠せない様子でした。


出発点は「問い」
あるグループは主要先進国の中で日本のリサイクル率がワースト1位であると知ったことをきっかけにして、リサイクル率が高い国と、日本のごみの処分状況を比較し、生ごみの処理方法に注目しました。
日本では、生ごみを燃えるごみとして焼却し、灰にして埋め立てています。この処理方法はリサイクル率に含まれないため、この点に注目すればリサイクル率の向上が図れるのではないかと考え、探究を進めました。
リサイクルは国ごとに法律や地理的な条件からごみの処理方法には向き不向きがあり、他国でうまくいっている方法が日本でもうまくいくとは限らないため、日本と環境が近い国や、同じ課題を抱える国の施策を参考に提案を行いました。
例えば韓国 では、食品廃棄物などをメタン発酵させることで、カーボンニュートラルな発電とリサイクル率の向上が可能となっています。
そこで、 日本でも生ごみを燃えるごみとして燃やすのではなく、肥料として再利用することで、リサイクル率を向上させることを提案しました。
この発表に対して、廃棄物・資源循環研究室の田中特別研究員は
「実は、生ごみを燃やすことは、衛生的に処理できるというメリットがあります。また、燃やして発生した熱の活用(サーマルリサイクル)をどう捉えるか、も大切な視点です。ごみとして捨てられたもの自体を資源として利用する以外にもリサイクルの方法はあります。リサイクルとは何なのか、考えてみてください。」とコメントしました。

別のグループは、日本の再生可能エネルギーによる発電量の中で、最も多くを占める太陽光発電をテーマとして取り上げました。
彼らは、大規模な太陽光発電所の建設にともなって行われるソーラーパネルの設置のため、景観や安全性をめぐって地域の住民から反発が起こるケースがあることに関心を持ちました。
同様の問題がさまざまな地域で起こっていることから、うまくいっている事例に着目し、再生可能エネルギーによる発電と地域・環境との共存を実現するにはどのような要素が必要かを検討しました。
このグループは、再生可能エネルギーによる発電が生物多様性に影響を及ぼす場合があるというニュースを見て「環境破壊される地域があっても再生可能エネルギーを活用するべきか?」という難しい問いから出発しました。
「“環境破壊”って何だろう?」「再生可能エネルギーを活用すべき状況ってどんなとき?」「どんなデータや情報があればこの問いに答えを出せる?」と、研究者から投げかけられたひとつひとつの問いに向き合いながら、グループで話し合い、探究を進めていきました。
これまでの講義で、再生可能エネルギーの利用が私たちの生活に重要であること、一方で生態系にも影響を与えていることの両方を知った彼らは、問いを「太陽光発電と環境保護をどう両立させるか」に変更し探究を深めました。
その結果、再生可能エネルギーによる発電と地域・環境との共存がうまくいっている事例では、地域の生態系の保護や住民との対話を丁寧に行っているだけでなく、太陽光発電所の設置によりその地域にとってもメリットを提供することが重要視されていることがわかったそうです。
これに対し地域環境創生研究室の五味室長は
「生態系の保護と大規模な太陽光発電所の建設は、現在活発に議論が行われている話題です。再生可能エネルギーの活用のためには避けては通れません。うまくいっていない事例も住民との対話の場を設けているケースも多くあるはずです。対話の場を設けてもうまくいかないのはどんな背景があるのかも検討してみたらもっと考察が深まると思います」とコメントしました。

今回の探究は、これまでの講義で学んだことの中からテーマを設定し、問いを立て、資料にまとめて発表する、という探究のサイクルの過程を経験しました。
今後は、自らの興味や関心にもとづいたテーマを自由に設定し、より主体的に探究を深める段階に入ります。
自分自身の興味を元に探究を深める楽しさを感じてもらえることを期待しています。





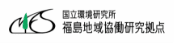
![講義から生まれた問いに向き合う。探究成果中間発表 [安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告③]サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/soutan2024_03_card.jpg)
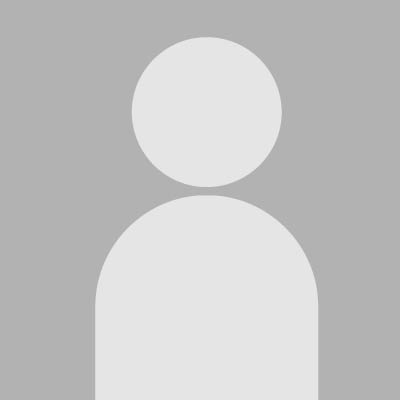
![講義と対話で環境を考える。私たちの持続可能な社会[安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告②]サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/soutan2024_02_card.jpg)
![高校生の探究をサポート。講義と対話で環境を考える[安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告①]サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/soutan2024_01_card.jpg)



