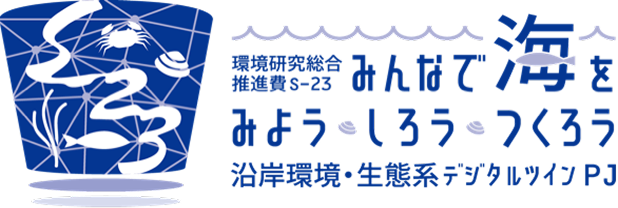NEWS新着情報
盤州干潟で合同調査が行われました

東京湾に広がる盤州干潟
梅雨を間近に控えた2025年6月11日から13日まで、盤州(ばんず)干潟においてS-23とモニタリングサイト1000の合同調査が行われました。盤州干潟は、千葉県を流れ東京湾に注ぐ二級河川、小櫃川(おびつがわ)河口付近から東京湾に広がる干潟で、広さ約1400haの広大な砂干潟です。東京湾アクアラインのアクアブリッジ陸側周辺に広がっています。
モニタリングサイト1000ってなに?
合同で実施されたモニタリングサイト1000とは、日本の自然環境を把握するために国が実施している調査で、日本全国に1000箇所以上の調査サイトを設置し、長期的にモニタリングを続けることで環境の変化をすぐに把握できるようになることを目的としています。


強い風と雨と
今回はS-23テーマ2のリーダー金谷さんをはじめモニタリングサイト1000に関わるいつものメンバーも合流しての調査です。
初日は雨と強い風が吹きつけるなか、遮るもののない干潟で強い風と雨を全身で受け止めながらも調査に集中する調査員たち。しかし悪天候とはうらはらに、干潟の生き物たちはそれぞれ自分のテリトリーの中でいつものとおり、悪天候なりに自分のすべきことをしているかのようでした。こちらが少しじっとしているとひょこひょこと出てきて動き回る小さなカニたち。海藻に隠れたエビたち。のこのこ動く小さな貝。砂に隠れた貝や見えないほど小さな生き物たち。調査員たちはそれぞれの種類を見つけては記録にとどめながら、次々とポイントをまわり、数値を測り、サンプルを採取していきます。午後になって天気が穏やかになり、蒸し暑くなっても黙々と調査を続けます。
蒸し暑さに負けない熱意!
2日目、3日目は晴天でした。晴天時には生き物たちの活動も雨の日とは違うようです。どんな種類が生息しているのか、例年と比べてどうか、生き物や干潟の状態の変化を見つけようと調査員たちの目も真剣です(もちろん調査用のサンプル以外はすべてリリースしています)。ときおり珍しい生物を発見すると、蒸し暑さも忘れて皆で集まって「すごいですね!」とねぎらい合う、そんな熱意と優しさのある研究者たちによって調査は着々と進められていくのでした。





今回の調査の意義
今回の調査によって、S-23テーマ2の干潟の生態系を知る手掛かりとしての重要な基礎データが、また一つ追加されました。
このような一つ一つの作業が積み重なって、この盤州干潟にはどんな生態系があるのか、自然環境の特徴や生物多様性を知ることができます。また温暖化、気候変動により環境影響で変化していく生き物たちの実態もうかがい知ることになります。

調査に参加された皆さん、暑い中の作業、本当にお疲れ様でした!
写真のキャプション 金谷弦(国立環境研究所)