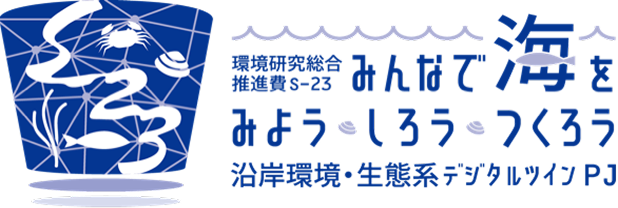NEWS新着情報
東博紀プロジェクトリーダーが関西万博でSATOUMIについてセミナーを行いました

2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)が2025年4月13日から開催されています。
各種各国、様々なテーマのパビリオンが盛況を呈する中、BLUE OCEAN DOMEにおいてシンポジウムが開催されました。BLUE OCEAN DOMEは、「海の蘇生」をテーマに、見えない海に目を凝らし、海の未来を考え続けるための交流拠点として様々な専門家が集い海についての情報発信を行う、特定非営利活動法人ゼリ・ジャパンが運営するパビリオンです。
パビリオンで開催されたイベント
「EDUCATION for BLUE OCEAN 地球市民が共創するブルーオーシャンの未来へ〜地域の資源を生かし、世界とつながる未来の海洋教育プラットフォーム〜」という海についての教育シリーズ 2回目のこの日のテーマは「SATOUMIと持続可能な海洋教育~阪南市の実践事例~」「『海の恵みを循環させる』自然資源と観光を活用し、教育原資を生み出す持続可能な仕組みづくり(ブルーエコノミーサークル:阪南モデル)」でした。その中ではまず阪南市長みずから『海の恵みを循環させる』持続可能な仕組みの実践例を紹介。次世代に海の知識を伝え、海の恵みをつなげていくことの重要度、効果や実践後の生徒たちの意識変化について説明しました。それに続き、自然資源と観光を活用し、教育原資を生み出す政策づくりについて、環境省水・大気環境局海洋環境課 室⾧補佐 森川政人氏による発表の中では、資源を守ると同時に経済効果を生み出す特産品づくりや名水などの認定といった工夫も紹介されました。
S-23研究プロジェクトに関する発表
国立環境研究所 地域環境保全領域 海洋環境研究室 東博紀 上級主幹研究員は「沿岸環境・生態系の統合的管理のためのデジタルツインプラットフォームの構築」についての発表を行いました。
まずS-23研究プロジェクトの内容と目的についてやさしく伝え、環境省の環境研究総合推進費によるプロジェクトであること、大阪府阪南市西鳥取漁協の波有手(ぼうで)の浜、西日本でも最もといえるほどたくさんの豊富な生物が棲んでいるこの浜をお手本にして海のデジタルツインを作ろうという取り組みであること、このデジタルツインを海の「見える化」のツールとして今後の予測や市民との議論に役立てようとしていること、日本のほかの浜にもそういう海を作るにはどうしたらいいのかを考えるうえでも役に立つということが説明されました。
海の「沿岸域」について
そもそも沿岸域というのは植物プランクトンが多くて有機物がとても多いという特徴があります。それは海の生き物にとってお野菜のようなもの。えさがたくさんあるのでそこには豊かな生態系が作られます。
この植物プランクトンは野菜と同じく、育っていくためには日光と栄養、適度な温度が必要です。でも最近の気候変動のせいで、温度が上がりすぎたり、雨が降らなかったり降り方が変わったことで海の中の食物連鎖が崩れ始めているのです。また黒潮の蛇行、これも気候変動のせいかもしれないと言われています。
海の変化をシミュレーションする
デジタルツインをつくる前の調査として日本の海がどう変化していくかというシミュレーションをしてみたところ、そのなかで一番の要素はやはり温度が3-4 度上がってしまうということだそうです。どの海域も水温が上昇し平均水温が30度くらいになってしまうとき、植物プランクトンの予測はどうなるでしょうか。調べてみたところ、水温が30度を超えると植物プランクトンは増殖できないようです。つまり、このままいくと(なんの対策もしない場合)、夏には暑すぎる水温のせいで植物プランクトンは減り、冬には少しだけ上がります。ということは、海の中全体のえさが減ってしまうということです。
もともと植物プランクトンは、冬には低温のため元気がなくなり数が減少し、夏には元気いっぱいでどんどん増えて赤潮の原因になるくらいでした。でも温暖化が進むにつれ冬にも植物プランクトンは元気になり、逆に夏はもはや暑すぎていわば焼け死んでしまうかのような状態になってしまいます。
そうなると何が起こるのでしょうか。報告が示すように近年アサリをはじめ漁業の全体的な漁獲量は減ってしまっています。栄養塩がないと食べるものが減ってしまうので海苔や海藻も元気がなくなって育つことができません。生き物たちの家(藻場)もなくなり産卵の場もなくなったり幼少期を過ごすには温度が高すぎたりして繁殖もうまくできなくなってしまいます。そのような負の循環を止めるという保全・再生・創出の活動が必要になるのです。
バーチャルに「海」を再現する
とはいっても専門家と一般の市民との間には見えている世界も理解度も大きく差があります。一般市民の方々がなにをすればいいか、知りたい情報をわかりやすく、また研究者の行っていることを手に取るように伝えることはできないでしょうか?そのためにはシミュレーションの結果を見えるわかりやすい形で提供する必要があります。そこで両者をつなぐ架け橋としてデジタルツインを開発しようというのです。
まだ開発途中で科学的知見が反映されていない状態ではありますが、バーチャルの海を作ってみました。ベースはゲームエンジンです。皆さんも一度はスマホなどでゲームをしたことがありますよね?海と陸との接合部分が水浸しのように映ってしまうなどまだまだ改善点は多くあるのですが、この中にさらに3Dの生き物を入れ込んで充実させていく予定とのことです。
このデジタルツインで目指しているものは何かというと、取り組みを評価したり、藻場や干潟の保全活動が湾全体にどのように広がっていくかを予測したり、科学的知見の見える化などです。
海というのは流れがあって繋がっているので湾と干潟や藻場、そこに棲む生き物も繋がっていたりするので広い視野で、網羅的に捉えていくことがとても大切だからです。
このように豊かな海を再生するためにいろんな挑戦がされている中でデジタルツインが「見える化」のバーチャルツールとして海洋教育に活用されたり、海にまつわるいろんな立場の人たちの意見を調整するためのツールとしても利用されること期待して研究を進めているとのことでした。
海の「見える化」としてデジタルツイン(を使ったゲーム?)を利用できる日もそう遠くはないかもしれません。