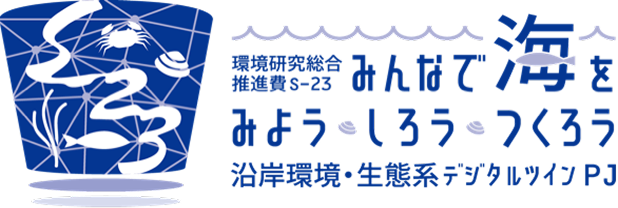NEWS新着情報
【記者レポート】大阪湾の底生動物調査に同行取材
2024年7月21日〜24日にかけて、大阪湾においてS-23テーマ2のメンバーが調査を行いました。テーマ2では自然共生サイトの生物多様性がどのように形成され、維持されているのか、またどのような生き物がいるのかといった知見をあつめ、S-23全体でつくるデジタルツインに反映するためのデータベースを作ることを目的としています。
今回はテーマ2の金谷リーダー率いるチームが、大阪湾に面する大阪府阪南(はんなん)市の海岸で行った調査にS-23広報担当者も同行して取材した様子をご紹介します。

自然共生サイトのひとつ、阪南セブンの海の森
「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」や「自然共生サイト」ということばをご存知でしょうか。「30by30」は、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標です。これは、生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現のために位置付けられています。
また、その実現に向けた取り組みのひとつとして、令和5年度から環境省が「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定してきており、森や海など、2025年2月現在では328か所認定されております。
私たちS-23の調査地のひとつである「阪南セブンの海の森」も、セブン-イレブン記念財団が阪南市とともにアマモの保護保全活動と沿岸清掃活動に取り組み、大切にされている自然共生サイトです。陸のサイトが多い中で、海のサイトはまだ数が少なく貴重な場所です。
阪南セブンの海の森に来た!
大阪市内のなんば駅から電車に揺られること50分、南海電鉄の車窓に海が広がるあのあたりが、阪南セブンの海の森です。
大阪府内で唯一の半自然海岸の浅場が広がることから、アマモなどの藻場があり、魚が産卵して稚魚がうまれたり、底生動物がすみかとしたりする、生き物の顔ぶれが豊かな海となっています。
生き物、の中でも底生動物調査
では実際、どのような生き物がいるのでしょうか。国立環境研究所のメンバーをはじめとする調査チームでは、2024年度に複数回の底生(ていせい)動物調査を実施しました。底生動物は水中や水辺に暮らす無脊椎動物で、貝やカニなどの甲殻類や、軟体動物などが含まれます。

調査風景
夏の調査は過酷です。強い日差しと高い気温、そして海辺では潮を感じるねっとりとした風。干潟の調査は水に浸かって行うことがほとんどですので服装も用意が必要です。長靴が胴まで伸びたようなウェーダーを着ますが、それがなんとも蒸し暑く体力を奪っていきます。小慣れた研究者は、夏場はスイムウェアを装備していました。

干潟に暮らす底生動物を探すためには、砂の中をみます。いくつかの地点を決めて、そこにどのような生き物が、どのくらいいるのか調べるために、決められた手法で調査します。




ソーティング作業
調査で集めたサンプルは、陸にあがって落ち着いて種類や数を数えます。小さな石と見間違えるような貝や、生きている貝ではなく抜け殻もあり、またピンセットでもつまみにくい小さな生き物など、とにかく集中して見つめ続けるソーティング作業が始まります。
見た目は同じようなにょろにょろとした生き物でも、見る人が見ると違う種類だときっぱり判別され、研究者の脳内にある豊富なデータベースから生き物の種名を特定して数えます。
真夏で大汗をかきながら海水に浸かって体力が消耗したあとなのに、その日のうちに集計を終える毎日が続くのです。苦行の日々かなぁと思いきや、地点により異なる生き物が暮らしていることに目を輝かせ続けている様子は、さすが研究者だなと唸ります。

なぜ底生動物を調べるのか
地点ごとに種類や数が異なる底生動物を調べるのはどうしてでしょうか。それは、底生動物が魚類などの餌となる生き物であることや、底生動物自身が有機物を取り込んで水質浄化をする機能などがあり、生き物や環境の関わり合いを知ることにつながります。
このような地道でかつ努力の必要な調査によって、この海にはどのような生き物がどのくらい生息しているのか、やっとわかるようになります。こうした調査手法はこれまでの研究で培われてきたノウハウが、世代を超えて継承されてきていることにより実現しております。
終わりに
調査を重ねることで、季節ごとのちがいや、なんらかの仕組みの解明につながること、S-23全体で目指すバーチャル空間での海の再現のための情報がより充実することなどを期待しています。今後研究が進み、成果のお知らせが出せる日をみなさまもぜひ楽しみにお待ちください。
日頃から調査・研究へのご理解・ご協力をいただいております関係機関の方々や地域のみなさまへも改めてお礼を申し上げます。
文・写真 志賀薫(国立環境研究所)
取材日 2024/7/20-24