2025/03/134分で読めます
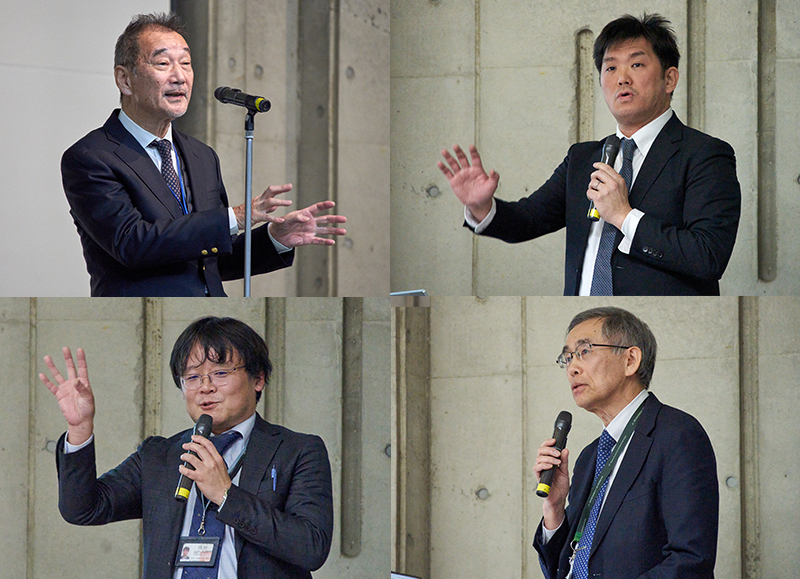
国立環境研究所では、「環境研究に関する研究発表、意見交換を通じて地方環境研究所と国立環境研究所の研究者間の交流を図り、共同研究等の新たな展開に役立てると共に、環境研究の一層の推進を図る」ことを目的に、「全国環境研究所交流シンポジウム」を昭和61年から毎年第4四半期に開催しています。
第40回目となる今回は、令和7年2月19日及び20日に、会場として国立環境研究所大山記念ホールの他、オンライン(Zoomウェビナー)を併用して開催されました。会場参加者は延べ82名、オンラインではアカウント数で203名の方が参加されました。オンラインということで、1アカウントから複数人の視聴があった可能性もあり、それを勘案すると更に多くの方々が視聴されたかと思われます。
木本理事長による開会挨拶でシンポジウムが開始され、その後には国立環境研究所 今藤室長による特別講演が行われました。この講演は、昨年度の地方環境研究所と国立環境研究所との協力に関する検討会において、環境DNA調査研究に対する技術的支援についての要望をいただいたことを踏まえて企画したものでした。もともと地方環境研究所の関心が高いテーマだったこともあり、大変ご好評いただけたのではないかと思っております。
特別講演のあとは、4つのセクションにおいて、2日間に渡り計17件の一般講演が行われました。また、国立環境研究所からの情報提供ということで、「環境研究共創拠点」の構築に向けた取り組みについても紹介させていただきました。講演題目と発表者については下記をご覧ください。
質疑については会場とオンラインの双方から受け付け、限られた時間内で活発な議論がなされ、それぞれの地域における環境問題に対する各地方環境研究所の取り組みについて、多くの知見が共有されました。
最後に森口理事の閉会挨拶をもって終了いたしました。
事後アンケートによると、地方環境研究所の研究者のほか、一般の方々も数多く参加されており、内容についてもご満足いただけたようでした。
地方環境研究所と国立環境研究所の研究者が一堂に会し、地域環境研究の最新動向を共有し議論する貴重な機会となりましたことを報告すると共に、ご講演、ご参加いただいた皆様や、企画・運営にご協力いただいた方々に深く感謝申し上げます。

《第40回全国環境研究所交流シンポジウム講演題目と発表者》*敬称略
【2月19日(水)】
特別講演
(1)「環境DNA解析の現場から:生物多様性観測における利点と課題」
〇今藤 夏子(国立環境研究所)
研究発表<環境DNA> 座長:今藤 夏子(国立環境研究所)
(2)「環境DNAメタバーコーディングにおける種の検出可能性の評価と研究デザインへの示唆」
〇深谷 肇一(国立環境研究所) (3)「昆虫類環境DNA調査の季節変化に関する基礎的検討-国Ⅱ型研究成果報告-」
〇長谷部 勇太(神奈川県環境科学センター) (4)「環境DNAが明らかにしたイトウ生息河川の魚類群集」
〇福島 路生(国立環境研究所)
研究発表<大気汚染> 座長:茶谷 聡(国立環境研究所)
(5)「名古屋市における大気浮遊粉じん中6PPDキノンの実態把握」
〇池盛 文数(名古屋市環境科学調査センター) (6)「ベイズ統計手法によるCMB法を用いた大気中微小粒子状物質(PM2.5)の発生源解析の検討」
〇花石 竜治(青森県東青地域県民局環境管理部) (7)「レベル3 建材からの石綿散逸問題に関するこれまでの取組みと今後の展開」
〇酒井 護(大阪市立環境科学研究センター)
研究発表<廃棄物・処分場> 座長:石垣 智基(国立環境研究所)
(8)「廃棄物埋立処分場の汚泥中のPFAS抽出条件の検討」
〇足立 里菜(大阪府立環境農林水産総合研究所) (9)「埼玉県における一般廃棄物最終処分場管理者との連携構築」
〇磯部 友護(埼玉県環境科学国際センター) (10)「最終処分場における事業者と研究者の連携によるデータの有効活用」
〇石森 洋行(国立環境研究所)
情報提供
(11)「環境研究共創拠点の構築に向けた取り組みについて」
〇白井 知子(国立環境研究所)
【2月20日(木)】
研究発表<気候変動適応> 座長:西廣 淳(国立環境研究所)
(12)「2種類の統計的手法による高解像度気候予測値の長野県における比較・検討」
〇栗林 正俊(長野県環境保全研究所) (13)「2100年三春滝桜の開花予測 -福島県における地域特性に即した気候変動影響手法の検討-」
〇蛭田 真史(福島県環境創造センター) (14)「上下水道局と協奏で行うAI 技術を応用した気候変動適応策の実施事例」
〇落合 孝浩、木村 和貴(郡山市環境部環境保全センター) (15)「改定で何が変わった?-地域気候変動適応計画のクオリティの変化に関する分析と評価-」
〇今井 葉子(国立環境研究所) (16)「北海道における将来の積雪変化の影響の理解に向けて」
〇鈴木 啓明(北海道立総合研究機構 エネルギー・環境・地質研究所) (17)「北海道における過去および将来の暑さの変化について」
〇大屋 祐太(北海道立総合研究機構 エネルギー・環境・地質研究所) (18)「市町村と連携した「暑さ指数」の認知度向上に向けた取組について」
〇米山 翔太(神奈川県環境科学センター) (19)「気候変動が暑熱健康に及ぼす影響とその適応に関する連携研究」
〇岡 和孝(国立環境研究所)
詳しい内容は、予稿集全文(下記のURL)でご覧になれます。
https://tenbou.nies.go.jp/science/institute/region/joint_zkksympo2024.pdf