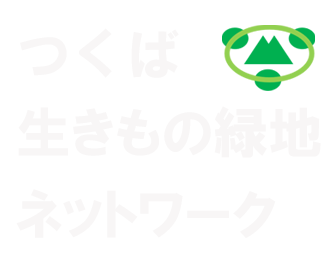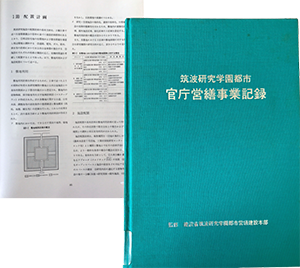2025年7月28日 第2回つくば生きもの緑地ネットワーク意見交換会を開催しました
国立環境研究所で7月28日に開催した「第2回つくば生きもの緑地ネットワーク意見交換会」には、現地参加26名、オンライン参加11名、合計37名の方にご参加いただきました。
今回のテーマは「土壌」。森林総合研究所の藤井佐織さん、産業技術総合研究所の佐藤由也さんから、それぞれ土壌に関する基礎知識や、土壌動物の多様性と土壌環境、土壌微生物の役割についてお話をいただきました。普段なかなか注目しない土壌の世界の奥深さに、参加者からは「面白かった」「知らなかった」という声が多くあがりました。
また、つくば市生物多様性地域戦略×土壌をテーマにしたグループディスカッションでは、活発な意見や土壌環境の知識をどう活動に応用していくか提案が飛び交い、参加者の皆さんの知識や経験の豊かさに改めて驚かされました。
回を重ねるごとに、業種や立場を超えたつながりが広がっており、「つくばの緑地」に関わる皆さんのゆるやかなハブとして、このネットワークが少しずつ育ってきていることを実感しています。