

|
●水の中の生き物への影響(えいきょう)
北ヨーロッパや北アメリカの国々では、酸性雨(さんせいう)によって、多くの川や湖が酸性化しました。その結果(けっか)、湖によっては魚が全くいなくなるなどの被害(ひがい)が出ました。
川や湖が酸性化すると、魚のえさとなる水中の昆虫や貝や甲殻類(こうかくるい)(エビなど)が減(へ)ってしまうことも知られています。また、水草など水中の植物も影響を受けます。
●森への影響
酸性雨によって土や水の性質が変わり、樹木の栄養分(えいようぶん)が不足したり、樹木に害のある物質(ぶっしつ)が取りこまれたりします。その結果、木が育ちにくくなり、森林全体が枯(か)れてしまうこともあります。森林(しんりん)には多くの生き物がすんでいるので、森林が枯れると、そうした生き物もすめなくなります。(酸性雨の原因(げんいん)となる二酸化(にさんか)イオウなどの大気汚染(おせん)物質が森林に影響をあたえることもあります。)
●建物や文化財への影響
軒下(のきした)などからコンクリートの「つらら」が下がっていることがあります。これは、酸性雨によってコンクリートの成分(せいぶん)のカルシウムが溶(と)けて空気中の二酸化炭素(たんそ)と反応してできた物質です。酸性雨は、コンクリートのほかにも、大理石の彫刻(ちょうこく)を溶かしたり、銅の屋根や銅像にサビを発生(はっせい)させたりします。
|
|
|
|
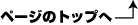 |
| |
|