

|
生き物がすんでいる山や湖、海などの場所とそこにすんでいるすべての生き物を含めて生態系(せいたいけい)と呼(よ)んでいます。
植物は、太陽のエネルギーを使って空気中の二酸化炭素(にさんかたんそ)と水から酸素(さんそ)と栄養分を作り、大きく育ちます。イモムシやウサギのような草食動物(そうしょくどうぶつ)は、植物がつくった栄養分を食べて生活しています。
また、モズやタカのような肉食動物(にくしょくどうぶつ)は、イモムシやウサギなどの草食動物を食べて生活しています。このように、生き物どうしは、食う−食われるいう食物連鎖(しょくもつれんさ)の関係でつながっています。
また、枯(か)れ枝や落葉は、カビやミミズなどによって分解(ぶんかい)されて、土にもどっていきます。森に降(ふ)った雨は、木の根をつたって土の中にしみこんでいき、時間をかけてきれいな水へと変わっていきます。
このように、生態系は、水や空気をきれいにして人間に供給(きょうきゅう)してくれるばかりでなくて、土砂崩(どしゃくず)れなどを防いだり、人間がすみやすい気候にしてくれたりします。このほかにも、生態系は、作物の育つ豊かな土や家畜のえさとなる草を作ってくれたり、
汚染物質(おせんぶっしつ)を分解してくれたりもします。生態系は、たくさんの生き物が野山や湖に生活することでなりたっています。人間が生き物を絶滅(ぜつめつ)させて、生き物の種類が少なくなっていくと、だんだんと生態系は水や空気をきれいにできなくなってしまいます。
生態系を飛行機(ひこうき)にたとえると、それぞれの生き物は飛行機の部品や部品をとめているネジみたいなものです。部品を止めているネジ1本がなくなっても飛行機は飛べますが、いくつかのネジがぬけ落ちると飛行機は空中分解をして墜落(ついらく)します。生態系のなかで、それぞれの生き物がどんな役割(やくわり)をしているか完全にはわかっていませんが、生き物が絶滅していくと、いつかは生態系も働かなくなり、きれいな水や空気を供給してくれなくなります。 |
|
|
|
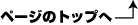 |
| |
|