

|
二酸化炭素(にさんかたんそ)の濃度(のうど)は、1万年くらい前から200年くらい前まで、ほぼ一定のあたいだったと考えられています。しかし、ワットが蒸気機関(じょうききかん)を発明して産業革命(さんぎょうかくめい)が起こった240年くらい前以降(いこう)から人間がエネルギーを大量 に使うようになりました。とくにそのころからエネルギーとして石炭や石油などの化石燃料(かせきねんりょう)が大量 に使われ出しました。これらを燃(も)やして電力に変えたり、自動車にガソリンなどを使う技術が進むと、人間のくらしは、よりいっそう化石燃料を使うようになってきたのです。
二酸化炭素の濃度の上がり方と、石炭・石油・天然(てんねん)ガスなどの使われ方をグラフでみると、その上昇(じょうしょう)カーブは、ぴったりと重なります。産業革命以前には、280ppm(ピーピーエム/1ppmは100万分の1の濃度)くらいでしたが、今では380ppmになっています。二酸化炭素濃度は、この200年の間に36%も濃くなっているのです。 交通機関(きかん)や電気製品(せいひん)が発達して、くらしは便利になったけれど、それと引きかえに、二酸化炭素が増(ふ)えてしまったのです。 |
 |
|
 |
|
|
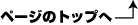 |
| |
|