

|
川や海にすんでいる生物(水生生物)の中でも、特に水底にすむ生物は、水のきれいさの程度(水質)を反映(はんえい)しています。いろいろな川にすむ生物を調べることによって、水の汚(よご))れの程度とそこにすむ生物の種類には関係があることがわかってきました。
水の汚れの程度の判定(はんてい)に使う生き物を「指標(しひょう)生物」といいます。総合的に水の汚れの程度を判定するために指標生物を使って調べる方法を「生物学的水質判定」といいます。
有機汚濁(ゆうきおだく)(家庭や工場、農地などからの排水にふくまれる有機物による濁(にご)った汚れ)が進むと、水の中に溶(と)けている酸素(さんそ)(溶存酸素((ようぞんさんそ))の量が少なくなります。
生物の中には、溶存酸素の量が少なくなると生きられない種類と、酸素の量が少なくても生きられる種類がいます。そこで、生物の種類を調べると、その川に溶存酸素が多いか少ないか、すなわち水が汚れているかどうかがわかるのです。
国では、川の中にすむ生物の中から30種類を指標生物に選び、その生物がすんでいるかどうかを調べて、川の水の汚れの程度を知る「全国水生生物調査」を行っています。この調査にはだれでも参加できます。毎年約8万人が参加していて、その80%は小中学生です。
「全国水生生物調査」に参加を希望される方は、国立環境研究所ホームページをご覧下さい。
http://mizu.nies.go.jp/suisei/
|
|
|
|
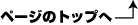 |
| |
|