

|
東アジア地域(ちいき)での数千年にわたる水田稲作(いなさく)を中心とする農業(のうぎょう)や人々の生活は、ごく最近まで、地域の自然環境(しぜんかんきょう)とよく調和(ちょうわ)し、うまくバランスのとれたものでした。
しかし、世界の各地では急速(きゅうそく)な経済発展(けいざいはってん)による開発にともなって、森林減少(しんりんげんしょう)、砂漠化(さばくか)、土砂流出(どしゃりゅうしゅつ)、水不足等が大きな環境問題となりつつあります。
近年、中国の長江(ちょうこう)(揚子江(ようすこう))上流の湖では、土砂が流入(りゅうにゅう)し、大雨などの時に、水をたくさんためておくことができなくなり、長江の中・下流域(かりゅういき)に洪水(こうずい)をたびたび起こしました。
長江流域(りゅういき)には中国の全人口の約40%がすんでおり、中国の経済発展(けいざいはってん)の中心となっています。しかし、近年の異常気象(いじょうきしょう)によって洪水(こうずい)がたびたび起こり、経済活動に大きな影響をあたえています。一方黄河(こうが)流域は、たびかさなる水不足により農業生産量の減少(げんしょう)や生態系(せいたいけい)への影響が問題となっています。
このため中国では、長江上流の湖などへの土砂の流入をふせぐために、ある角度以上の斜面(しゃめん)の耕作地(こうさくち)を森林に戻すという(退耕環林(たいこうかんりん))政策(せいさく)を開始しています。森林には雨水をたくわえるという動きがあります。さらに雨水が斜面の土にあたって、そこがけずられてしまうのをふせぐのにも役立ちます。
このように、人間の活動が水の循環をくずした結果(けっか)、結局人間に被害(ひがい)がおよぶということが最近の研究でつぎつぎと明らかになってきました。
|
|
|
|
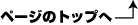 |
| |
|