

|
1960〜1980年ごろの日本の工場地帯の空気は、とても汚(よご)れていました。工場の煙突(えんとつ)から出るけむりや、自動車の排気(はいき)ガスで、青い空が見えないほどでした。そのため、ぜんそくや気管支炎(きかんしえん)に苦しむ人もたくさんいました。
その後、工場から出るけむりや自動車の排気ガスは、規制(きせい)され、工場地帯の空気は、少しずつきれいになってきました。
ところが、こんどは自動車がとても増(ふ)えたため、自動車の多い大都会では、空気がなかなかきれいにならなくなってきたのです。とくに、ディーゼル車は、ガソリン車にくらべて排気ガスをきれいにすることがむずかしいため、これまで空気の汚れの大きな原因(げんいん)となってきました。
このような人間の活動による空気の汚れを大気汚染と呼(よ)んでいます。大気汚染を引きお起こす物質(ぶっしつ)には、浮遊粒子状(ふゆうりゅうしじょう)物質やチッ素(そ)酸化物(さんかぶつ)、イオウ酸化物、一酸化炭素(いっさんかたんそ)などがあります。 |
| |
|
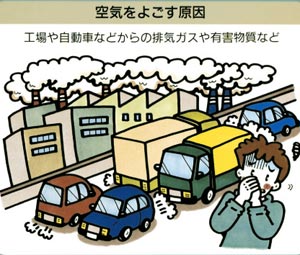 |
|
|
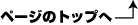 |
| |
|