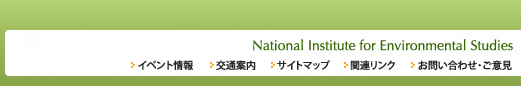1-3.研究成果の積極的な発信と社会貢献の推進
1-3-(3).社会貢献活動の推進
研究成果の国民への普及・還元を通じて、社会貢献に一層努める。具体的には、以下の取組を推進する。
1-3-(3)-1.研究成果の国民への普及・還元活動
ア.公開シンポジウム(研究成果発表会)、研究施設公開の実施
6月に開催予定の公開シンポジウムや7月に開催予定の研究所施設の公開イベントにおいて、最新の研究成果について、研究者から直接国民にインパクトのあるメッセージを発信する。
イ.各種イベント、プログラムへの参加
シンポジウムやワークショップ等の開催又は参加に努めるほか、環境省や地方公共団体等とも連携し、環境保全を広く国民や地域社会に訴えるイベントや、若い世代に環境研究の面白さを伝えるためのイベントやプログラムにも積極的に参加する。
ウ.研究所視察者・見学者の対応
視察者・見学者の希望を十分把握した上で、研究活動に支障のないよう留意しつつ、視察者・見学者が満足するような見学コースの設定に努める。なお、見学対応においては、展示内容や展示方法を工夫しつつ、わかり易く興味を持てる説明に努める。
Ⅰ 業務の実績
1.公開シンポジウム、研究施設公開
(1)公開シンポジウム(研究成果発表会)
国立環境研究所公開シンポジウム2011「ミル・シル・マモル 〜命はぐくむ環境を目指して〜」をよみうりホール(東京、平成23年6月18日)及びシルクホール(京都、同6月25日)で開催し、それぞれ、546名、224名の参加を得た。シンポジウムでは、研究所の東日本大震災後の復旧復興貢献に向けた取り組みについて4つの緊急報告と研究成果等に関する3つの講演、18テーマのポスター発表を行った。また、講演内容の分かりやすさ等についてアンケートを実施した。アンケートでは、「どれも分かりやすかった」、「おおむね分かりやすかった」との回答が多くよせられた。なお、講演に用いた資料等については、過去のものも含め、わかりやすく整理してホームページに掲載するなど、フォローアップも行った。

「国立環境研究所公開シンポジウム2011」の様子
(2)一般公開
1)一般公開については例年、春と夏の2回行っているが、平成23年度は東日本大震災による施設等の被災により、4月の一般公開を中止した。夏の一般公開は平成23年7月23日(土)に、「夏の大公開」として開催した。来訪者数は、3,811名であった。(資料32)
2)夏の一般公開では子どもから大人までの全ての年齢層を対象に、講演や研究施設の説明だけでなく体験型イベントや環境学習的な展示等もとり入れ実施した。特に23年度は、東日本大震災からの復旧・復興に関する研究所の取り組みや、夏の節電対策についてパネル展示等を行った。また今まで以上に公共交通機関を利用した来所を推進するため、22年度に引き続き産業技術総合研究所と連携して無料循環バス「環境研・産総研号」を運行したほか、JRひたち野うしく駅との間で無料バスの運行を行い、自家用車の使用抑制を図った。

国環研「夏の大公開」の状況(平成23年7月、つくば本所内)
2.各種イベント、プログラムの開催・参画
(1)研究成果の普及・還元の一環として、国立環境研究所の主催、共催で各種シンポジウム、ワークショップ等を開催した。国内では、第1回 生物影響試験実習セミナー、ブループラネット賞受賞者記念講演等14件、国外ではベトナム低炭素社会国際モデルキャパシティ・ビルディングワークショップ、フィリピンにおけるE-waste問題啓発ワークショップ等10件を開催した。(資料33)
(2)また下表に示すとおり、若い世代も含めた幅広い年代層を対象とした、環境研究・環境保全に関するイベント・展示会等に協力した。このほか、特に若い世代に対するイベントとして、後述のとおりサイエンスキャンプ、つくば科学出前レクチャー等に積極的に参画した。
| 参画したイベント等 | 開催時期 | 実施内容 |
|---|---|---|
| エコライフ・フェア2011 | 23年6月 | 代々木公園に専用ブースを出展し、侵入種や地球温暖化に関する研究成果を多くの方に説明した。 |
| つくば市節電大会 | 23年6月 | つくば市主催のイベント。家電等の買い換えにより、家庭からのCO2排出量がどの位削減できるのか、模型を使って考える体験イベント等を行った。 |
| うしくみらいエコフェスタ | 23年10月 | 牛久市の主催イベント。自転車発電により、家庭からのCO2排出量がどの位削減できるのか、考える体験イベントを行った。 |
| つくばサイエンスコラボ2011 | 23年11月 | つくば市主催のイベント。自転車発電や家電等の買い換えにより、家庭からのCO2排出量がどの位削減できるのか、模型を使って考える体験イベント等を行った。 |
| TXテクノロジー・ショーケース 2012 | 24年1月 | 研究所の概要パネルの展示を行った。 |
| 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議(nano tech 2012) | 24年2月 | ナノテクノロジーを用いた環境保全技術に関する展示等を行った。 |
3.研究所視察者・見学者への対応
(1)平成23年度における視察者・見学者の受入状況は次のとおりである。(資料32)
国内(学校・学生、市民、企業、官公庁等) : 50件 804人
海外(政府機関、研究者、JICA研修員等): 29件 371人
(2)見学対応による研究者等への負担を軽減し、一層の効率化を図りつつ対応能力を向上させる必要があることから、基本的な見学コースを設定し、企画部門スタッフによる説明対応を充実させるとともに、パネル等の展示スペースの新設や、施設見学用のパンフレット、DVD、パネル、展示物等の整備、改善を進めた。
- このリンクはPDFデータにリンクします(資料32)平成23年度研究所視察・見学受入状況 [PDF:738KB]
- このリンクはPDFデータにリンクします(資料33)ワークショップ等の開催状況 [PDF:337KB]
Ⅱ 自己評価と今後の対応
平成23年度の公開シンポジウム(東京及び京都)のアンケート結果によると、研究成果や研究所の東日本大震災での取り組みについて一般の人々から高い関心が示され、講演内容についても高い評価が得られた。
夏の一般公開では研究所全ユニットをあげて対応した結果、多くの来場者に研究所の活動成果の普及を図ることができた。また公開に際し、産業技術総合研究所との交通連携など引き続き実施し、公共交通機関を利用した環境負荷の少ない来所を推進することにより来場者に環境への関心を高めることができた。アンケート結果によれば、大部分の来場者から研究内容に興味をもてたとの回答を得られ、わかりやすく効果的な一般公開が実施できた。
また平成23年度は「つくば市節電大会」等地方公共団体主催のイベントにも積極的に参加し、地域社会や若い世代の環境研究への関心を高めることができた。
平成24年度においても、アンケートの結果も踏まえ、公開シンポジウム、一般公開、視察・見学対応等を通じて、研究所の研究成果をさらに分かりやすく社会・市民に伝えるよう努める。
視察者・見学者への対応については見学終了後アンケート調査を行っており、適宜そのアンケート調査結果をフィードバックし、効率的かつ効果的な見学を実施していく。
1-3-(3)-2.環境教育及びさまざまな主体との連携・協働
ア.環境問題の解決のためには、社会構造やライフスタイルの変革等国民の具体的な行動に結びつけることが重要であることから、第1の2の環境情報の提供のほか、各種体験学習プログラム等の実施又は参加により積極的な啓発活動・環境教育に取り組む。
イ.環境問題に取り組む国民やNGOを含む関係機関等に対して、適切な助言や必要に応じて共同研究、講師派遣等を行うことにより一層の連携・協働を図り、地域や社会における環境問題の解決に貢献する。
Ⅰ 業務の実績
高校生など次代を担う青少年を対象に、環境保全に関する知識や情報を普及・啓発し環境教育を行うことを目的として、サイエンスキャンプ等の教育プログラム等に積極的に参画した。
また、要請に応じて「つくば科学出前レクチャー」や各種団体等の主催する講演会・学習会等に研究者を講師として派遣して環境保全に関する講義を行い、環境保全活動を行う学校や市民を支援した。さらに、市民団体等の研究所の見学を積極的に受け入れ、研究成果の紹介や環境保全活動のための助言等を行った。
| 普及・啓発・ 環境教育活動 |
時期 | 対応内容 |
|---|---|---|
| サイエンスキャンプ2011 主催 (独)科学技術振興機構 対象 高校生・高専生 (1〜3学年) | ①23年7月 27日〜 29日 ②23年8月 15日〜 18日 |
①「環境と生物」(つくば本構、10名) 土壌微生物から抽出した特定遺伝子の増幅・分離実習等により生物の多様性について学習。 ②「東京湾の魚介類と環境を調べてみよう」(東京湾(横浜市)12名)底曳き網による魚介類収集を行い、東京湾で進行中の生態系の変化について学習。 |
| 講師派遣 | 要請に応じ随時 | つくば科学出前レクチャー(つくば市)、おもしろ理科先生(茨城県)等の地方自治体による事業や市民グループ等からの要請に応じて講師を派遣し、環境研究に関する講義等を行った。 |
Ⅱ 自己評価と今後の対応
平成23年度は、サイエンスキャンプ、つくば科学出前レクチャー等への講師派遣など積極的に協力・活動を行うことができた。引き続き、環境教育及びさまざまな主体との連携・協働に努めていく。