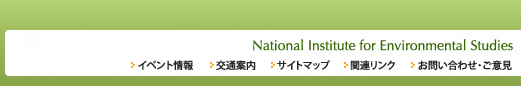2.資源循環・廃棄物研究分野
研究の概要
1.第3期の研究活動の背景としての第2期の研究内容と成果
第1期、2期を通じて、「循環型社会形成」と「廃棄物管理」の両面から研究を推進してきた。以下、両者を分けて第2期を振り返る。
(1)循環型社会形成に関する研究
第2 期において「循環型社会重点研究プログラム」を4 つの中核プロジェクトで構成して推進し、国内の近未来の循環型社会ビジョンづくり(中核PJ1)、資源循環過程における環境リスクの管理(中核PJ2)、バイオマスを中心とした技術システムの開発(中核PJ3)、アジア大の国際的な循環資源の移動と環境問題・アジア新興国の廃棄物管理(中核PJ4)に関するそれぞれの研究テーマにおいて以下のような目標について成果を得 た。
中核PJ1:近未来のシナリオ作成と物質フローモデル構築、モデルに基づく環境負荷の評価、技術システムやマネジメント手法の設計評価
中核PJ2:家電製品等を対象とした有害性・資源性からの管理方策枠組提示、臭素系難燃剤の暴露評価、金 属の資源ポテンシャル、リサイクル製品安全評価
中核PJ3:エネルギー/マテリアル循環利用技術の開発と評価、バイオマス系地域循環システムの技術面からの設計と評価
中核PJ4:アジア地域での物質フロー分析による越境移動把握、制度分析、リサイクルによる環境影響把握、途上国における準好気性埋立実証実験と液状廃棄物処理の適合条件提示
個々のPJ における残された課題については、
中核PJ1:低炭素社会や自然共生社会との統合的アプローチ、国レベルと地域レベルの具体的政策、経済評価など
中核PJ2:総合的なリスク評価と循環過程でのリスク管理、資源性と有害性の観点からの物質管理政策の具体化と効果予測評価
中核PJ3:地域特性に応じた技術システム像、社会実装に向けた実証化
中核PJ4:
また、中核PJ 間で有機的連携を図り、中核PJ1 と3、あるいは中核PJ2 と中核PJ4 の一定の融合は図れた。しかし、それぞれの中核PJ 自体の守備範囲が広すぎて、ファクトを積み重ねるだけの成果になった点も否めず、「循環型社会」の形成に向けて、一つの大きな概念づくりには至らなかった。
(2)廃棄物管理に関する研究
安全・安心な適正処理・処分技術(最終処分、破砕選別中間処理、焼却技術評価)、試験評価モニタリング (次期POPs、バイオアッセイ包括的毒性評価)、液状・有機性廃棄物の適正処理技術(し尿・浄化槽)、負の遺産対策(廃PCB対策、堆積廃棄物の発火メカニズム・予防方策)、石綿分析法と精度管理手法などについて、政策対応や現場的に活用可能な知見を得るための調査研究を実施した。得られた成果については、一部は現場的なマニュアルなどに反映されるなど、貢献した。しかし、行政側とのコミュニケーション不足により、環境行政の先を見通した成果の発信が出来ていない面もある。研究の実施にあたって、地方環境研究機関との連携を行っており、現場や地域的政策ニーズへの対応も積極的に行っている。
2.第3期における研究活動内容と達成目標
(研究プログラム、環境研究の基盤整備を含む)
「循環型社会形成」と「廃棄物管理」については、行政上も研究上もアプローチは異なる側面があるが、今期5 年間では、両者の結節点において新たな概念を提示できるように、資源循環・廃棄物研究分野において以下のような研究を推進する。
(1)循環型社会研究プログラム
日本とアジアの近隣諸国にまたがる国際的な資源循環、アジアの開発途上国の廃棄物適正管理、国内の地域特性を活かした資源循環という三つの地域区分に着目して、廃棄物の適正管理を資源の有効利用や地球温暖化対策との協調のもとで行うための科学的・技術的知見が求められる課題に取り組み、国内外の循環型社会構築を支援。国内地域から世界(アジア圏)までの安定かつ環境効率性の高い資源循環と廃棄物管 理、それを支える社会システムづくりに貢献する。
研究活動内容と達成目標は以下のとおり。
PJ1:国際資源循環に対応した製品中資源性・有害性物質の適正管理の視点から、3R を促進する適正管理方策について、物質(製品、素材を含む)のフロー把握・解析と製品ライフサイクル挙動調査に基づいて検討する。資源性・有害性物質の適正管理に資するマテリアルフロー・サプライチェーン及び環境影響の解明、及びESM(環境上適正な管理)の基準の考え方など、国内及び国際的に通用する政策的な見通しを与えることを目標とする。
PJ2:アジア地域に適した都市廃棄物の適正管理技術システムの構築の視点から、日本国産の埋立技術や液状廃棄物処理技術等のカスタマイズと廃棄物管理システムの導入支援ツールを開発、実装を目指して適合化を図る。それによって、途上国における環境問題解決と温暖化対策をリードするための廃棄物処理に関するハード及びソフト技術の明示、及び適正な廃棄物管理システムを実際の都市や地区へ実装するための計画手法を提示する。
PJ3:地域特性を活かした資源循環システムの構築の視点から、様々な地理的規模において、その地域特性を活かしつつ適正な資源循環システムを構築するための枠組みの提示とシステム設計・評価し、実装につながる取り組みを行う。それによって、地域活性化や地域振興と調和した循環型社会づくりに貢献、さらに学術的には資源循環の適正な地理的規模を推定する論理や地域における資源循環利用のための概念設計を行う。
(2)資源循環・廃棄物研究分野の研究(循環型社会研究プログラム以外)
政策対応型の着実に実施すべき廃棄物管理に関する研究を推進するとともに、将来を見通し、当該分野の新しい研究の柱となるような萌芽的な基盤的研究課題にチャレンジする。研究の活動概要と目標は以下のと おり。
① 固形・液状廃棄物に対する従来技術の評価・改良、新規技術の開発を行い、システムの管理戦略等を提示
② 石綿や廃POPs 等の難循環物質及び不法投棄・不適正処分場を対象として、分析調査、リスク評価,修復 及び管理に関する一連の手法を提示
③ 公的制度の構築、東アジア等との制度共有展開に貢献するよう、再生品の環境安全品質レベルの設定、 品質管理の枠組み・検査法の標準化
④ 廃棄物処理・資源化に係る基盤計測技術と性状評価手法を開発、資源化・処理に係る要素技術の開発
⑤ 将来の資源需要と国際物質フローの構造解析手法、物質ライフサイクルにおけるリスク管理方策
⑥ 独自の資源化技術や環境修復再生技術等の社会的実現を早期に達成し、地域環境再生政策に貢献するよう、外部連携を推進
(3)資源循環・廃棄物研究分野における環境研究基盤整備
5年、10年といった中長期視点から戦略的に我が国やアジア圏における資源循環・廃棄物研究の情報基盤構築を先導・実施により、我が国における資源循環・廃棄物研究の中核拠点としての機能を果たす。 具体的な事項は以下のとおり。
① 我が国における資源・物質利用、廃棄物処理の長期データの整備
② 資源のフローデータや資源利用に伴う環境負荷に関するデータ整備
③ 廃棄物等に含まれる循環資源の賦存量データ整備等
④ 廃棄物の分別区分や有料化等自治体政策情報の整備や処分費用データ
⑤ アジア圏を対象とした国際廃棄物管理に関するデータの調査・整備
[外部研究評価委員会事前配付資料 (PDF 736KB)]
第3期におけるミッション/研究体制/研究の概要/ 別添資料
委員会からの主要意見
[現状についての評価・質問等]
○ 実施内容、目標・計画はおおむね妥当と考えられる。
○ リサイクルに関しては、他の研究機関との連携をとりつつ行うと、社会に対して実効性のある研究が展開できるのではないか。
○ 重点プログラム(循環型社会研究プログラム)について、他の分野や研究センターとどのような連携・役割分担のもとで研究を進めていくのか。
○ 東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理に関して、震災対応ネットワークから迅速に各種レポートが出たことは、高く評価できる。
[今後への期待など]
○ アジア地域全体の廃棄物適正管理についてリーダーシップを発揮する必要がある。
○ ライフサイクルアセスメント(LCA)に関する研究強化とサプライチェーンに関するデータベースの構築に期待する。
○ 災害廃棄物処理への取組みについては、安全適正な処理の観点に加えて廃棄物の有効利用にもつながっていくと良いのではないか。
主要意見に対する国環研の考え方
① 資源循環・廃棄物研究分野の推進にあたっては、他の研究機関をはじめ、関係業界や企業、国や地方自治体、国際機関等と連携しつつ対応していくことが重要と考えています。このため、資源循環・廃棄物研究センターにおいて今期より「研究開発連携推進室」を新設し、社会に対して実効性のある研究が展開できるよう、国内外の様々な機関との連携を推進します。
② アジア地域の廃棄物管理研究の拠点機能を発揮するための体制整備を図っており、その端緒として、本年度は埋立研究に関するアジア地域の若手技術者育成プログラムを実施しているところです。
③ リサイクルについては、発生側から最終利用先まで様々な業界が関わっており、関係する業界団体や研究機関と連携をさらに深めていきたいと考えています。LCAやサプライチェーンのデータベース化についても、所外の研究者と連携しつつ研究を着実に進め、国研としての役割を果たしたいと考えます。
④ 東日本大震災による災害廃棄物や放射能汚染廃棄物問題への対応については、これまで国内研究者・技術者で構成される震災対応ネットワークを活用しつつ、廃棄物資源循環学会等の一員としても、現地調査・巡回を積み重ね、各種技術情報の提供、現場関係者への助言・指導、緊急調査研究の実践などを通じて、処理に関する基準・指針等の策定や現場での処理推進に積極的に貢献してきました。今後も、国や地方自治体、関係機関との密接な連携を図りつつ、使命感を持って、災害廃棄物や放射能汚染廃棄物の迅速かつ円滑な処理と再生利用の推進に貢献したいと考えています。
⑤ 重点研究(循環型社会研究)プログラムをはじめ上記の各種取組にあたっては、低炭素・自然共生・リスク低減などの他の研究分野との協調・融合が重要であり、所内の他の研究センターと適切に連携していく所存です。