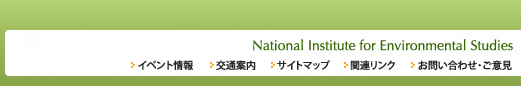2.循環型社会研究プログラム
5年間の研究概要
今後の循環型社会構築に向けて、わが国の循環型社会の近未来像、資源性・有害性をもつ物質の管理、バイオマス系廃棄物の資源化技術、資源循環・廃棄物管理の国際的側面、という切り口から、4つの「中核研究プロジェクト」において重点的に取り組むとともに、他の研究ユニットの研究者が主体となる「関連研究プロジェクト」4課題を実施した。また、廃棄物管理の政策課題に直結した調査・研究にも重点的に研究資源を配分するとともに、本分野の中長期的な問題への対応、解決に資する研究能力の向上を図るための基盤的調査・研究や知的研究基盤整備についても、本重点研究プログラムの一部として一体的に推進した。
[外部研究評価委員会事前配付資料 追跡調査シート(PDF 286KB)]
研究開始時の背景と5年間の研究概要/第2期の事後評価結果と対処方針/学術的貢献/社会・環境政策などへの貢献・波及効果/研究成果の発表状況等
外部研究評価委員会からの主要意見
[学術的貢献について]
○ 廃棄物処理の技術研究・開発、廃棄物管理に関する物質挙動解明等の理工学研究と、循環型社会の管理システム、社会シナリオ等の社会科学研究の両面において、それらを融合しつつ他の研究所にはできない独自の成果を上げ、センターの存在感を示してきた。また、学術的成果に結びつけることが困難な内容にもかかわらず、様々なデータベースの構築も含め、個別の学術的成果公表が続いている。
○ 各中核プロジェクトを貫くコンセプトが見られないため、プログラム全体の目指す循環型社会の構築に近づけておらず、製品生産段階から3R、エネルギー、コストを意識した産業構造や消費社会構造にパラダイムシフトを促すような学術貢献は不十分である。研究資材、物的・人的資源の合理的・効率的利用のため、大学、関連研究機関、企業等とより一層の共同研究を促進して欲しい。
[社会・環境政策などへの貢献・波及効果について]
○ 第2次循環基本計画の改定やOECD等における資源管理等で、多くの成果が活用されるとともに、専門的知識の提供でも大きく貢献している。また、今般の震災における行政との密接な連携を可能なものとした背景には、廃棄物管理に関する理工学的な、地味ではあるが着実な研究蓄積があったことが大きく貢献している。さらに、経済・物流・人流のグローバル化に伴って、アジア全体を見据えた研究活動が進められている。
○ 廃棄物処理から資源管理の考え方に転換するための新たな産業構造のあり方など、「循環」を巡るより大きなコンセプト作りが必要である。また、所内社会科学系との連携により、経済性や社会受容性など、社会実装施策策定に関し、循環型社会への推進力や遷移過程に着目した現実的な検討と情報発信が必要である。さらに、アジアの国を中心に3R思想を広め、国際資源循環の確立をめざして欲しい。
主要意見に対する国環研の考え方
○ 4つの中核研究プロジェクトを貫く循環型社会の共通概念が十分議論されていない点はご指摘のとおりです。第三期中期計画における新たな循環型社会研究プログラムを推進する上での中心課題として議論していきたいと考えています。その際には資源問題の視点をより重視し、資源安全保障の観点も含めて国際的スケールで研究していきたいと考えています。さらに、産業構造や消費社会の構造のあり方を問い直すための新たなパラダイムづくりも必要であると考えています。
○ 以上のような新たな展開において、現在の研究者リソースでは難しい面がありますので、社会環境システム研究センターなど他センターとの連携や、大学、関連研究機関、企業等との外部連携により、分野横断・セクター横断的な共同プロジェクトなども模索していくべきだと考えています。また、実証的な取り組みのフェーズで統合的な研究アプローチをとっていくことで、経済性や社会受容性など、社会実装施策策定に関し、循環型社会への推進力や遷移過程に着目した現実的な検討と情報発信を図ることが可能になると考えています。