わが国における
中核的環境研究機関のビジョン
平成10年9月
国立環境研究所
「わが国における中核的環境研究機関のビジョン」
目次
Ⅰ.ビジョンの背景
Ⅱ.中核的環境研究機関の基本方針
1.基本的理念
2.創造的な環境研究・技術開発のための基本的視点
3.環境研究における基本的アプローチ
Ⅲ.総合的な環境研究の進め方
Ⅳ.中核的環境研究機関の役割
1.学際的・総合的な研究推進
2.重点的な研究推進
3.横断的なネットワーク研究推進
Ⅴ.中核的環境研究機関の規模・機能・組織
1.規模
2.機能
3.組織
Ⅵ.研究評価
Ⅶ.付録
I.ビジョンの背景
「21世紀は環境の時代」である。その意味は、この世紀において地球環境保全が、人類共存の戦略を遂行する上で、最も高いプライオリティを獲得する事であり、人類共通の超大型プロジェクトになることであろう。
いうまでもなく、来世紀には人口過剰、食糧不足、資源枯渇そして環境破壊といった、閉鎖系としての地球に住む人類の存続にかかわる諸問題が、私たちの文明自体を脅かすことが認識されてきている。しかし局所的に視るならば、今世紀においても、以上の諸問題に対する適切な対応能力に欠ける地域では、21世紀的混乱と悲劇がすでに生じているのが判る。例えば、人口爆発から環境破壊、さらに食糧不足から部族対立を激化させた国や、過剰灌漑によりアラル海を消失させつつある中央アジアの国々、それに続いて、同様の破局を起こすおそれのある国々のリストは大きくなる一方に見える。
地球、あるいは地域を問わずこうした環境問題に対する新たな対応努力は、1990年代に入って各国でなされてきている。わが国では1993年に環境基本法が制定され、翌年政府は環境基本計画を策定した。そこには大量生産、大量消費、大量廃棄型経済から、「循環」を基調とする経済・社会システムへの転換の実現、自然生態系の一員としての人間が多様な生物種と「共生」することへの意欲、そして地球環境保全は全ての主体の「参加」のもと、究極には「国際的取組」によらねば達成されないとする認識がくみとれる。全地球的取組の例としては、1997年、地球温暖化防止京都会議(COP3)において、人間活動が地球気候変動を生ぜしめる一因であることを、160に上る国々が史上初めて一致して認めたのである。
このようにわが国のみならず世界の環境科学研究の成果には数々見るべきものがあったにもかかわらず、人間活動の規模はそれを上回る勢いで増大し、環境問題は局所から全地球へと拡大していった。また、環境問題は時空間においても拡大し、人類の未来や種の保存が課題となってきている。たとえば内分泌攪乱物質による汚染は、次世代の健康に影響を与え、これにより環境倫理の中心的原理「後代へ安全な環境を伝えること」さえ遵守できないのではないかと危惧される。
21世紀を迎えるに当たって、わが国の環境研究はどのような変革をなすべきか。その回答は、陣容・規模を格段に強化増大した「中核的環境研究機関(Center of Excellence for Environmental Studies, COEES)」を設定することと考えられる。COEESは下記の5つの視点から正当化されよう。
第1に「Sustainable Development」で表現される人類の生存の長期的安定性や生物多様性等で表現される自然環境の保全を求めるための研究には、十分な研究基礎を長期的に維持した大規模の研究機関が必要である。
第2に、地球環境を保全し、国内及び各地域の人々の健康を守り自然保護に資する研究の展開をわが国の国家戦略として選択するとすれば、国民、NGO、産業界などとも協調した、国家的な意志を体現した研究機関が必要である。
第3に、今や人類は後代に安全な環境を残せないかもしれないという過去に遭遇したことのない危機的状況にある。このような緊急事態に即応して、国内外の英知を結集し、後代のリスクを推定し、適切、迅速に対策を講じることができる研究機関が必要である。
第4に、地球及び地域の環境研究において、人文科学・社会科学から理工学、農学、医学にいたる多様な自然科学の真に総合的でかつ緊密な内部交流が行われることが必要である。
第5に、全国の大学、研究所、地方環境研究機関などの国内研究ネットワーク、UNEP、国連大学、UNIDO、WHO、ILO、OECDなどの国際機関、更にはアメリカ、欧州、アジアなどの各国の環境関連・学術研究機関との国際ネットワークのもとに共同研究を行うことが必要であり、その中核となる研究機関が必要である。
国立環境研究所は、1974年に深刻化する公害問題に対応して、わが国の社会の要請に応じて国立公害研究所として誕生し、基礎から応用までを含む学際的な研究を展開し、公害研究のナショナルセンターとしての機能を果たしてきた。1990年には研究組織を改組し地球環境の保全と自然環境の保全への所掌研究領域を拡大し、環境研究におけるわが国の中心的な研究所としての役割を果たしてきた。この対応は今まで立派に成功してきたといってよい。しかし環境問題の広域化と深刻化はそれらの対応を超えた新しい体制を要求している。21世紀には、国際社会において日本が指導力を発揮しつつ、全地球環境保全という目標にどのくらい迫り得るかが環境問題の核心となろう。そして国内外にむけて日本が説得力ある環境政策を推し進めるには、中核的環境研究機関を発足させ、そこに国立環境研究所が積極的に参画し、その中心的役割を担うことが必要となろう。

II.中核的環境研究機関の基本的方針
1.基本的理念
人間活動は現実に人間とその環境に対し地球のいたるところで、脅威を与えるようになった。進行する環境汚染・破壊への対応の基礎となるべき環境研究の拡充強化は、国内のみならず国際社会の要請である。環境研究は、人間活動が環境に与える負の影響を配慮しつつ良好な環境を保全することにより、人間生存がつつがなく全うされることを目的として、将来の環境のあるべき姿を明確にしなければならない。従って高くかかげるべき基本的理念としては、国際社会への貢献、国民の環境問題理解・行動への貢献及び環境政策への貢献を挙げることができる。
2.創造的な環境研究のための基本的視点
1)社会的に顕在化する前に環境問題の本質を発見探索的に認識し、通常援用されない学問分野の方法をも含めて自由な視点に立ち、新たな研究方法を開発する。これによって本質的変革を達成し、独創性を発揮することを重視した研究が必要である。このことは研究のみならず、研究管理や制度の改革にも適用されるべきである。(先見性に基づくブレークスルー)
2)人類が直面する環境問題に関する研究には、環境問題の本質の洞察、関係諸問題の相互関係の認識、文明史や人類存続の本質に対する理解、関係諸学問の寄与に対する先見性、諸外国における研究動向などを十分考慮した戦略的取り組みが必要である。このため、国際的な視野で環境研究の戦略をたて、それに基づく研究を企画立案する機能を持つことが重要である。(ナビゲーション機能)
3)研究機関の運営管理において、研究資源の配分の柔軟さ、研究者のテーマ設定の自由さが重要である。それらが研究成果の評価に基づいて個々の研究者や研究組織に的確にフィードバックさせる等により、研究者の潜在的能力を発現させ、活動を活性化させることが必要である。(インセンティブと競争的環境)
4)世界をリードする研究成果をあげていくために、独創性の高い研究を推進する必要がある。次項の目的指向型研究、先導的基礎研究、共有知的基盤型研究を相互に密接に関係させるとともに、国際的に成果を発信し、その実効性を高めていく必要がある。 (国際的競争力)
5)世界に誇れる中核的研究機関であるためには、十分な研究資金、人的資源を持ち、研究スペースと設備等の整備された研究機関であることが必要である。また、創造的な環境研究を展開させるには、研究者の特性を理解し、意欲のある研究者が働きやすい環境を保証することも重要である。このため研究機関としての自己管理能力をもった独立性が堅持されなければならない。(研究機関の自律性)
3.環境研究における基本的アプローチ
中核的環境研究機関は、環境問題の主として戦略的研究を展開する研究機関であり、研究のカテゴリーには以下のごときものがある。
1)目的指向型研究
社会的要請に応えて、最も重要と考えられる問題をとりあげ、各分野の専門研究者の有機的連携による体系的研究の推進をはかる。すべての環境研究は人間と生態系との関連に視点をおいて展開されるべきであり、その範囲は環境変動の現象解明・予測、その人間や生態系への影響評価・予測、予防的対策、劣悪化した環境の修復等の手法の開発、更には持続的発展が可能な社会システムの構築のための研究、及び環境政策研究等におよび、これらが密接不可分の関係を有している。研究の遂行には多くの学問分野が協同して対処するため、その研究体制は自然科学、社会科学及び人文学を含めた学際的かつ目的指向型のものとなる。
2)先導的基礎研究
未知の環境問題を探索発見するためには、既成認識の盲点を明らかにし、研究者の知的関心と独創性に発する研究を、重視する必要がある。また環境問題の展開を予測して行くためには、自然や社会の長期間の変化と相互影響を見通し、かつ幅広く関係要因の抽出に目配りした研究が必要とされる。
3)共有知的基盤型研究
本機関は環境問題の多様化や広域化に伴い、環境研究の円滑な推進を図るためにネットワークの中核機関として機能しなければならない。国内外における環境データ、研究情報の整備、環境研究に係わる各種試料や遺伝子資源の保存、環境モニタリング等、環境研究の知的基盤の体系的整備を行う。知的基盤なくしては全ての研究は停滞し、ブレークスルーは不可能となる。したがって、それに資する研究および技術開発を推進し、その成果を広く国際的ネットワークで共有する必要がある。当然、これらの知的基盤は環境研究以外の社会的要求にも応えることをも意図している。
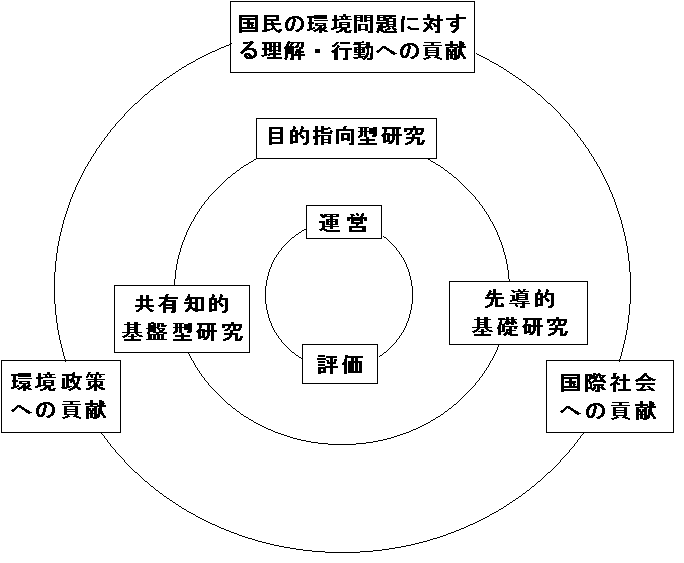
III.総合的な環境研究の進め方
環境問題解決のためには分野横断的研究技術開発を総合的に実施していく必要がある。このため政府全体の環境関連研究に関する基本方針の作成を行う環境科学技術会議(注)と、その下に事務局の機能を果たし一元化された環境研究予算の研究企画立案、研究費配分、研究評価を行う推進機構を設置する。本会議及び本推進機構は環境研究の専門的見地より、分野横断的な研究企画・管理機能を発揮するものとする。
米国、欧州連合においてはGDPの約0.1%が環境関連研究費として計上されており、世界をリードすべき我が国の環境研究の費用としては同程度の割合である5,000億円程度が妥当と考えられる。この環境関連研究予算額は、従来は各省庁で個別に計上されていた環境関連研究予算をすべて一元化させ、今後の環境問題の重要性に鑑み研究費を拡充させ、上記程度の予算枠を設定する。環境科学技術会議のもとに中心的に位置づけられる中核的環境研究機関には環境研究予算の約20%(米国の医学関連の中核研究機関であるNational Institute of Health(NIH)に準じた割合)にあたる約1,000億円程度を配分し、先端的環境研究の推進にあたらせるとともに、その成果を環境科学技術会議の環境科学技術政策に反映させる。
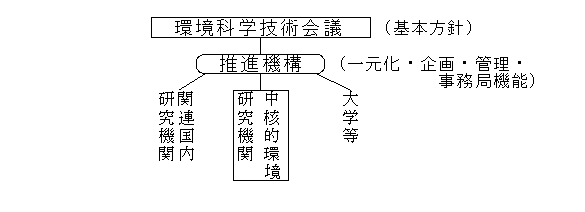
(注)総合科学技術会議と環境科学技術会議との相互の関連については、別途行政的な視点からの検討も必要であろうが、いずれにしろ、環境研究は広範かつ総合的な学問体系であり、このような観点に立って環境研究の進め方を大局的に検討しうる場の設定が必要である。
IV.中核的環境研究機関の役割
人類が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続の基盤である限りある環境を将来にわたって維持することは我々の責務である。そのため環境への負荷の少ない循環を基調とする経済社会システムへの転換を実現していくための理念や、健全な生態系を持続・回復し自然と人間との共生を確保していくための理念を提示し、その実現に向けた予見的・予防的環境保全政策や技術を提供する必要がある。環境研究は、環境の変化の把握・機構解明・将来予測、人の健康や生態系に対するリスクの解明・評価、環境保全に資する各種の技術の開発、環境政策の提示といった環境問題の解決に向けた各種の自然科学的又は社会科学的及び人文学的な調査研究であり、環境保全の基礎となる科学的知見や技術的基盤を提供するものである。
「環境基本法」(1993年)及び「環境基本計画」(1994年)の中でも環境研究の分野における重点的・効率的な取組みが求められている。環境研究は、1)国及び国民の安全や福祉等市場原理になじまず、2)研究投資の高リスク・高負担を伴う先端的・先導的であり、3)基礎的・基盤的科学技術をもっとも必要とし、4)国際協力の推進に資する研究分野である。このため民間企業のみでは実施困難な研究分野であり、国が中心的役割を担い、産業界、大学、地方自治体及びNGOとも密接に連携を保つことにより、我が国の環境科学技術の発展に努め、人類の知的資産の形成に努める必要がある。
1.学際的・総合的な研究推進
環境問題は事象相互の関連が複雑多様であることから、縦割体制のもとでの個別の研究を断片的に実施しても解決への有効な成果が得られにくい。とりわけ最近の環境問題の広域化と深刻化は従来の枠組みをこえた新しい学際的・総合的研究体制をとることを要求している。中核的環境研究機関の第一の使命として、今後長期ビジョンに基づく戦略的研究計画の策定を行い、国際社会の中での責任を考慮しつつ、我が国全体の環境研究を総合的に推進することが求められている。
2.重点的な研究推進
本機関の次の使命は、環境を視点とする新たな価値観の創造、環境システムの複雑性・不確定性の低減、国際的な(特にアジア太平洋地域に対する)環境研究のリーダーシップをとることにより、21世紀の環境問題解決と人類社会の持続的発展に資する研究開発を行うことである。中核的環境研究機関としての使命を達成するため、今後10年間に重点的に推進する研究として、「今後の環境研究・環境技術のあり方に関する検討会(平成9年6月)」の検討結果を踏まえて、主として
1)戦略的環境モニタリングの実施
2)生物多様性の解明
3)地球環境変化の予測
4)環境の総合的管理
5)環境リスクの低減
6)低環境負荷型社会の構築
7)環境政策手段の提示
に係わる研究を学際的な体制のもとに推進していくことが必要である。
3.横断的なネットワーク研究推進
中核的環境研究機関は国内の他の環境関連研究機関との横断的共同研究、ネットワーク化推進の先導的かつ中心的存在としてパートナーシップに基づく環境研究のリーダーシップを積極的に担っていくことが必要である。さらに国外の中核的環境研究機関との国際的連携を強化し、環境研究の国際的役割分担とその総合化を推進する。
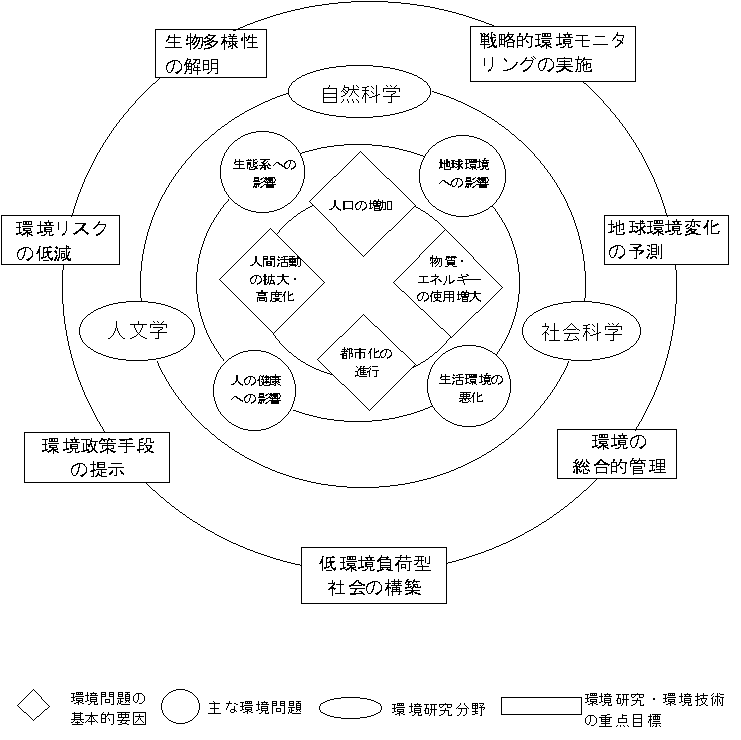
V.中核的環境研究機関の規模・機能・組織
環境研究分野で最先端を維持し、世界をリードする研究成果を挙げるには、制度運用の柔軟性を高め、創造的で競争的な研究組織を作ることが重要である。
1.規模
環境科学技術会議のもとに、中核的環境研究機関をおく。この研究機関は、それ自身において先端的環境研究を行うほか、多くの環境研究機関を結ぶネットワークの結節点やハブとしての機能も果たす。なお、研究者数は当面は1000人、10年後には3000人を目標とする(例えば国内環境問題にのみ対応している米国EPAに属する研究所の研究者の数はおよそ3000人である。)
2.機能
中核的環境研究機関は5つの機能を有する。即ち、1)基本的方針において示される目的指向型研究、先導的基礎研究、共有知的基盤型研究を学際的、総合的、計画的に実施する「研究機能」、2)環境研究の知的基盤の体系的整備を行い、研究機能の円滑な推進を保証する「研究支援機能」、3)優秀な若手研究者育成のために必要とされる「人材育成機能」(例えば学位授与等)、4)国内外の他の環境研究機関との横断的共同研究、ネットワーク化推進の先導的かつ中心的役割を果たす「ネットワークの結節点やハブとしての機能」、5)国際的視野で環境研究の戦略を構築し先導する「ナビゲーション機能」を有する。
3.組織
わが国全体の環境研究を総合的に推進するうえで必要な上記機能を果たすために、研究組織、研究企画管理組織及び研究支援組織の3つの組織をもつ。
1)研究組織
研究機能及び人材育成機能を果たす研究者の組織として、研究分野別のコアラボラトリーをおく。プロジェクト研究はコアラボラトリーの人材を集約して問題に対応できる柔軟な体制とする。コアラボラトリーは任期なし研究員及び任期付き研究員、ポストドクトラルフェロー、大学院生等をもって構成する。各コアラボラトリーが各研究分野における国内外の環境研究機関間のネットワークの結節点としての機能も果たす。
2)研究企画管理組織
ナビゲーション及びネットワーク機能を果たす組織として、国際的視野で環境研究の戦略を企画、立案、計画、調整するとともに、制度運用の硬直化を防ぎ、自由かつ創造的で競争的な研究機関及び連携する多くの研究所群の全体的な企画管理運営を実施する組織を設ける。
3)研究支援組織
研究支援機能を果たす組織として、フィールド研究や各種実験に必要な専門的研究支援技術者の組織、モニタリングの実施組織、データベース及び環境情報を管理する組織等を設ける。これらの組織の業務管理はそれぞれの組織の長のもとに行う。
Ⅵ.研究評価
研究の評価には、研究機関の運営管理の評価、研究管理者の評価、研究課題の評価及び研究者の評価とがある。評価にあたっては、評価の原則・方針・項目・基準を明確にすると共に、公平性や透明性を担保し、その評価は、的確に運営に反映されるものでなければならない。
評価の概念については下図及び付録参照。
Ⅶ.付録
中核的環境研究機関におけるプロジェクト研究の執行、人事、研究費等の運用及び研究評価は、本機関の設立が現実化した段階で、その状況に応じて弾力的に実施されるべきであるので、現時点ではそれらの概念を付録として示す。
1.中核的環境研究機関の運用について
1)プロジェクト研究の執行
研究プロジェクトを起こす場合には、プロジェクトを提案して採択された者がプロジェクトリーダーとなる。所外者もプロジェクトの提案資格を有し、採択されたときはプロジェクト研究の実施期間に相当する任期を付して任期付きコア研究員相当職として採用する。
プロジェクトリーダーはプロジェクト実施のため、プロジェクトチームを編成する際に、コアラボラトリー構成員をその身分のまま採用するほか、コアラボラトリーに属さないポストドクトラルフェロー、大学院生等で構成する。
2)人事
中核的環境研究機関は、その構成員の選任にあたって、広く国内外に人材を求めるよう配慮する。
任用にあたっては、任期付き雇用をとりいれて、柔軟な人事運営を達成する。また、研究者の自由度を拡大し、例えば研究者は、研究遂行に差し支えがない限り、研究機関外との兼職ができるものとする。 支援組織構成員の処遇の決定には、研究者とは別個の考課原理を以て行う。
3)研究費
目なし研究予算、多年度にわたる研究費運用、多年度にわたる研究費配分等の予算運用上の自由度を十分に確保する必要がある。
2.研究評価(図参照)
研究の活性を持続させるためには研究の評価を公正に行うことが必要である。評価の対象は研究機関自体(長を含む)、研究管理者、研究課題そして研究者である。
1)研究機関の評価
研究機関の機能を最大限に発揮できるように研究機関の運営全般(組織、人事管理、研究活動、研究課題の選定、研究資金・資源の配分、施設・設備・情報基盤、研究支援体制の整備、外部研究機関との交流・共同研究、その他)及び機関の長を対象に評価し、評価結果を研究機関の改善や更なる発展にフィードバックさせることが必要である。
環境研究の中核機関としての評価の実施にあたっては、研究成果の質と量、社会的ニーズへの対応、新たな研究領域・方法の創出能力、環境研究分野における国際的な先導力、国際的な貢献度、組織の効率的な運営等を指標とし、これらの指標から環境研究の中核機関としての評価を行うことが必要である。
評価は国民の意見を広く反映させるような評価者からなる外部評価委員会で行うべきである。必要に応じて外国の卓越した研究者を評価者とすることも有効である。
2)研究管理者の評価
研究課題や研究計画に対する評価の妥当性などを指標にして研究管理者の適性と能力を評価することは研究機関全体の運営を健全にし、より良い開放的な研究の場の創出につながる。評価の内容としては企画力、管理能力、PR力、予算獲得能力、組織化能力等が含まれる。評価は研究者が行うことにより均衡と緊張関係を確保すべきであるが、同時に研究管理者間の相互評価も重要である。
3)研究課題の評価
研究者から提案された研究課題は、まず事前の評価を加えることによって内容の充実を図る。さらに、中間および事後(最終)評価を行うことにより一層の充実を図ることも必要である。特に、事後評価は中間および事前評価の妥当性を評価することにもなる。また、新たな課題の提案の材料を提供することにもなる。評価は研究管理者が主体となり遂行する。
4)研究者の評価
研究者の評価には研究能力の評価と研究課題遂行能力の2つの評価軸が考えられる。研究能力は論文数、掲載論文誌のインパクト係数、論文の引用件数、特許数、特許の実施状況、学会賞、招待講演数等で評価されるが、論文の出にくい分野についての考慮が必要である。また、学問分野によってはその慣習と必要性から、重要な原著研究成果が、著書、商業専門誌、あるいはwwwによって発表され、評価されることがあることも考慮しなければならない。いずれにせよ、このような公表された研究成果は、それが目的指向型研究であれ、先導的基礎研究であれ、共有知的基盤型研究であれ、環境問題の認識ないしは解決に寄与するかどうかという視点からも評価されなければならない。
研究課題遂行能力は研究課題やチームへの貢献度、研究費に対する成果の質、環境問題対応への貢献の大きさ等で評価される。評価は研究管理者が行う。評価の結果は公表し、より研究成果が上がるようにフィードバックする。
5)将来計画への反映
評価結果を環境研究の更なる展開に反映させるためには、5年、10年単位の環境研究の将来計画を策定し、研究機関全体の中長期的研究の方向性を明確に示すことが必要である。将来計画の提示は次なる研究テーマのための予備研究や先導的基礎研究に取り組む機会を生み出す源になるだけでなく、研究組織の改廃や研究費の配分等を計画的かつ重点的に行う道標となり、結果として質の高い研究成果を引き出すことになる。
6)広報活動の積極的展開
環境問題の現状と将来について、不断に、広く国民に理解を求めることが環境研究を遂行発展させる上で大きな前提となる。このため、環境研究の研究目的や内容・成果、予算の規模や使途について、十分な透明性を担保しつつ、国民の理解と支援を得ることは今後ますます重要である。この意味で、広報活動の積極的展開は中核的環境研究機関の重要な責務の一つと位置づけるべきである。