環境試料タイムカプセルとは
環境試料の長期保存研究は、一般に環境試料バンク(あるいは、スペシメンバンキング,Environmental Specimen Banking : ESB)と呼ばれており、国内外の多くの研究機関・大学で、それぞれ特色ある環境試料を収集・保存しています。
国立環境研究所では、1979年から環境試料の長期保存を行っており、2002年から"環境試料タイムカプセル化事業"という名前で、新たに環境試料と絶滅危惧生物(動物・藻類)の細胞等の遺伝資源保存を開始しました。

環境試料については、これまで-20℃での保存が主体でしたが、2004年の環境試料タイムカプセル棟(環境試料・遺伝資源長期保存施設)の完成によって、液体窒素雰囲気下(-150℃)での本格的な保存継続体制が整いました。この施設を利用し、日本の環境を代表する各種の環境試料を体系的に収集・保存し、その中の汚染物質濃度を測定することで、環境汚染物質の50〜100年にわたる長期的トレンドを調べることを環境試料タイムカプセルでは目的にしています。
これらの試料は、将来起こりうるあらたな環境問題の発生や新しい汚染物質の顕在化、新規に開発されるであろう高度な分析法によって利用・解析されることを想定して、長期保存されています。試料に含まれる汚染物質ばかりでなく、汚染物質への曝露によって生物側に引き起こされる影響(特定の遺伝子やタンパク質の発現、生体分子との反応生成物などバイオマーカーと呼ばれるもの)の保存も目指して、凍結状態での試料調製と液体窒素雰囲気下での保存により、試料をできるだけ変質させない条件で長期保存を行っています。

環境試料・遺伝資源長期保存施設は、随時見学を受け付けていますが、試料の汚染防止のため、上のイメージのような液体窒素保存容器をガラス越しに見学していただき、研究概要についてはパネル展示で説明しております。
どんな試料を集めているのか
現在、環境試料タイムカプセルでは、魚類や貝類、海底堆積物、大気粉じん試料、母乳などさまざまな試料を収集しています。二枚貝試料、特にイガイ類は日本だけでなく世界各地の沿岸域に広く分布しています。イガイ類を用いた環境モニタリングは、マッセルウォッチと呼ばれ、その地域の汚染の状態を調べる優れた方法です。
二枚貝試料は、東京、名古屋、大阪、福岡などの人口密集地と、離島などのバックグラウンド地点で、毎年サンプリングを行います。その他、毎年場所を移動して日本全体をカバーする移動採取地点があります。
東京湾では20地点で、年4回底曳き網調査を行い、魚種別の個体数と重量の精密調査をするとともに、アカエイなどを保存試料とします。
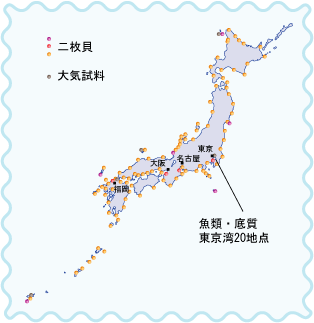
上図は、ムラサキイガイなどの二枚貝類採取地点を示したものです。10年程度の頻度で、離島を含む日本全体の沿岸域を調査する予定です。
フィルター上に捕集された大気粉じん試料は、-60℃の保存庫で長期保存し、母乳試料は、-80℃の冷凍庫で長期保存します。
試料の種類ごとの採取地点や結果については、別に詳しくまとめてあります。
どのように保存しているのか
環境試料を50年間以上長期保存するためには、試料の変質を最小限に抑え、さらに、試料に対する人為的な汚染のない保存試料を作る必要があります。そのために、試料をできるだけ低温に保つことを心がけます。いったん凍結した試料は、その後は解凍することなく、凍結粉砕法により微粉末とします。
試料の調製法を順を追って示してゆきます。
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
 |
 |
 |
| 液体窒素による現場での二枚貝の凍結 | アカエイから肝臓を取り出す | スタンプミルでの粗粉砕 |
(1) 各地で採取した二枚貝類は現場で処理し、液体窒素凍結します。
(2) 東京湾で採取したアカエイは即日、研究所内で肝臓を取り出します。
(3) 凍結した試料は、最初に粗く粉砕します。金属チタンでできた臼のような形をした粉砕器(スタンプミル)に試料を液体窒素とともに入れ、突き崩すように粗く粉砕します。この操作で5mm程度の試料となります。
| (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|
 |
 |
 |
| ボールミルでの微粉砕 | ビン詰めされた粉砕試料 | 液体窒素保存容器への収納 |
(4) さらに、チタン製のボールミルを用いて凍結状態のまま微粉砕します。写真のように凍ったままの細かい粉になります。その粒径の中心は50ミクロン程度です。
(5) 将来の利用に備えて、1つの試料は複数のガラスビンに蓄えられます。凍った粉末は温度が上がるとドロドロになってしまうため、低温で素早く作業します。
(6) 液体窒素雰囲気(約-150℃)の保存容器で長期保存されます。
粉砕した試料は粒度分布と無機元素の測定により均質性を確認します。
粉砕過程での汚染を避けるためクリーンルーム内で作業し、定期的に実験室などの状態や粉砕過程での汚染検査を行っています。
どんなことがわかるのか
環境試料タイムカプセルを利用することで、次のようなことに役立ち、未解明のことがらに対応できると考えています。
まず第1に、試料を集める段階での分析を通じて、その時点でのさまざまな物質の環境中の濃度レベルがわかります。この分析を毎年継続して行くことで、汚染物質や環境の状態長期的な変動や、日本全体にわたる空間的な広がりを描き出すことができます。下図には新たな汚染物質として注目を集めている有機フッ素化合物(PFOS, PFOA)の二枚貝中の濃度分布を示します。
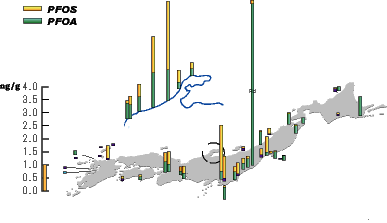
また、保存した試料をまとめて測定することで、分析手法や分析する人の技術的なかたよりが少ない、一貫した最新の方法で精度の高い過去の試料の解析やモニタリング技術の向上につながります。その結果、環境中のわずかな変動を見逃すことがなくなると考えます。
さらに、例えば下図に示したタンカーの座礁によるオイル漏れ事故の場合などのように、ある地域が汚染された場合、その地域の過去のバンキング試料と事故以降に採取した試料を比較することで、その地域の汚染の深刻度や事故後の環境修復の程度が確認できます。
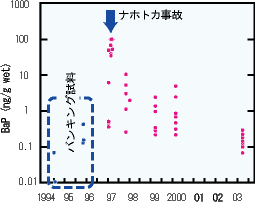
将来あらたな環境問題が発生したり、今まで知られたことのない汚染物質が問題となった場合、タイムカプセル試料を取り出して、その問題がいつ頃から広がり始めたのか、その汚染レベルはどの程度であるのかといった疑問に答えを与え、対策に道を開きます。そのためには、あらゆる用途に耐えるような試料を作り、保存していかねばならないと考えています。
施設の諸元
長期保存室
400L 液体窒素タンク 19基(うち環境試料用10基)
収容可能試料数 9,000本(50ml容ガラスビン)
液体窒素自動供給、自己診断機能
活性炭素繊維フィルタークリーンルーム(クラス10000相当)
低温室
-60℃ 67m2 2室
収容可能試料箱 1,920個(1箱50L)
フリーザー室
-80℃ ディープフリーザー7台
活性炭素繊維フィルタークリーンルーム(クラス10000相当)
試料調製室
液体窒素供給口
活性炭素繊維フィルタークリーンルーム(クラス10000相当)
分析前処理室
活性炭素繊維フィルタークリーンルーム(クラス10000相当)
分析機器室
LC/MS/MS(Applied Biosystems), ICP-MS(Agilent)
GC-QMS, GC-HRMS, GC-ECS, PCGC, マイクロ波分解装置
液体窒素タンク
7.7m3


