

|
ダイオキシン(炭素(たんそ)、酸素(さんそ)、水素(すいそ)と塩素(えんそ)からできている)は、山火事や火山の爆発(ばくはつ)によって自然(しぜん)界にもわずかですが生成します。日本では塩化ビニルなど塩素をふくむ合成樹脂(ごうせいじゅし)や食品をふくむ生ゴミなどの焼却処分(しょうきゃくしょぶん)により大量に発生していました。平成9年12月にダイオキシン発生量を大幅に低減(ていげん)する焼却炉に関する規制(きせい)が強化され、ゴミ焼却にともなうダイオキシンの発生量は大きく減少(げんしょう)しました。
また、かつて水田などにまかれた農薬(のうやく)中にも不純物としてふくまれていました。ダイオキシンは、環境(かんきょう)中では分解(ぶんかい)がむずかしいため、今でも残念ながら環境中に残っています。
ダイオキシンとは、ひとつの物質のことではなく、200種類以上の化学物質(ぶっしつ)をまとめて呼(よ)ぶときの名前です。その中にはがんを促進したり、ホルモンの働きを乱す種類があり、動物の種類によっては毒性の影響(えいきょう)を非常に強く受けるものもあります。
新しい設備(せつび)を持っていないゴミ焼却場(しょうきゃくじょう)の煙突(えんとつ)から発生したダイオキシンは、風に乗って地面に降(ふ)りつもり、土壌(どじょう)や水から生物に取りこまれて、やがてそれらを食べる人間や動物の体にたまって、害をもたらすことが心配されています。
|
| |
|
 |
|
|
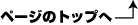 |
| |
|